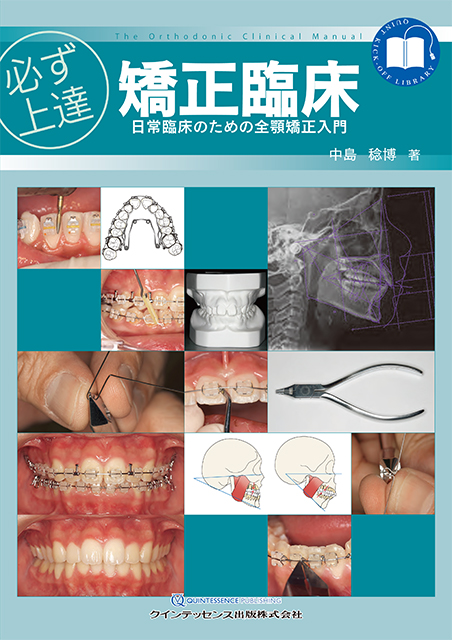2020年2月9日掲載
「トラブル症例から学ぶ歯科臨床―その傾向と対策―」のテーマで総勢650名を集め盛況となる
第44回北九州歯学研究会発表会開催

最初のプログラム「中野充先生追悼講演」は、当初下川氏が担当する予定であったが氏の急逝を受け、松延彰友氏と村上和彦氏が登壇し、中野氏のすぐれた人格や臨床的功績、さらに要職にも就いていた歯科医師会での活躍などにふれ故人を偲んだ。
続いて、去年のテーマでもあった「挑戦 Part2」では中野氏のご子息である中野宏俊氏が「父の背中と症例を追いかけて~保存への挑戦~」と題し、父親と自身の症例を比較しながら、保存治療について語った。松延允資氏は「エムドゲインを用いた再生療法への挑戦」のタイトルで他家骨であるDFDBAにエムドゲインを混和した骨移植材を用いて再生療法を成功へと導く手法について説明した。樋口克彦氏の「歯冠形態を考慮した前歯部コンポジットレジン修復への挑戦」では、前歯部の正中離開をコンポジットレジンで修復した症例やその経過を提示し、修復とその後のリカバリーの視点でレジン修復が語られた。
昼食を挟み、メインセッションとなる「トラブル症例から学ぶ歯科臨床―その傾向と対策―」では咬合編、ペリオ編、インプラント編と3つに分けられ、それぞれ甲斐康晴氏、白石和仁氏、榊 恭範氏が登壇した。甲斐氏は「歯列咬合の影響を考える」の演題の中で、咬合治療の流れは歯牙単位・歯列単位・咬合単位と広げて考えることの重要性を説いた。続く白石氏は「トラブル、トラブル、トラブル」というキャッチーなタイトルで登壇し、自身の10年以上経過した長期症例でその後トラブルが起きたケースを供覧し、なぜ経過不良が起こるのかを考察した。最後の榊氏は、「NO IMPLANT、NO LIFE」と題し、予後20年を超えるインプラント治療のトラブル症例を惜しげもなく提示し、10年後の想定されるトラブルにマイナーチェンジで対応できる治療計画を立てるべきだと後進たちに警鐘を鳴らした。
各発表の後には必ず質疑応答の時間が設けられ、会場の参加者と活発な議論が交わされていた。
※なお、実名を挙げた歯科医師の先生方はすべて福岡県開業