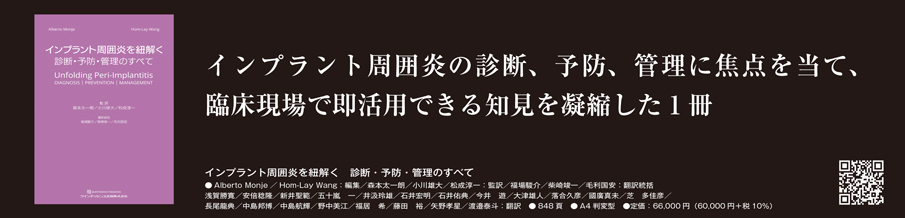2025年10月号掲載
インプラント周囲炎のすべてを制す!
【PR】 インプラント周囲炎に対する 知識と希望を与える書籍!!
※本記事は、「新聞クイント 2025年10月号」より抜粋して掲載。
小社7月の新刊として、『インプラント周囲炎を紐解く 診断・予防・管理のすべて』が刊行されました。本欄では、水上哲也氏(福岡県開業)に本書の特徴や読みどころ、活用法などについて語っていただきました。(編集部)
Wang氏とMonje氏による
インプラント周囲炎の最新情報
さる5月に、オーストリアのウィーンで開催されたユーロペリオに参加した。1万人規模の巨大な学会で参加者の多さと熱気に圧倒された。その展示会場で『Unfolding Peri-Implantitis』(※編集部注:『インプラント周囲炎を紐解く 診断・予防・管理のすべて』の原著)を目にして早速手に取ってみた。美しく拡大された見やすい症例写真に加え、周囲炎についての詳細かつ豊富な情報が記載されており、その場で購入することを考えた。しかしながら、たいへんページ数が多く重量感のある書籍であること、そして日本語による翻訳本が出版予定であることを知っていたため、思案の末に購入を思いとどまり帰国した。そして今回、すばらしく訳された本書が出版され、待っていて良かったと感じている。
本書は、臨床的な立場、そして基礎的な立場の双方からの最新の知見が収載されている。この20年ほどの間に、インプラント周囲炎についてこれほどまでに深い理解がなされ、予防法やメインテナンス、そして治療が進歩してきたことに驚く。
本書の編者の一人であるHom-Lay Wang氏はインプラント学、歯周病学において世界をリードする著明な研究者であり、かつすぐれた臨床医である。800本以上にのぼる論文は被引用数76,515を超える偉大な研究者でもある。近年ではインプラント周囲炎に関する著書や論文も多く、この分野においてもすぐれた業績を残している。現在彼が提唱しているEP-DDS(詳細は後述)はインプラント周囲炎の治療に取り組む臨床医の新たなプロトコルになろうとしている。
もう一人の編者であるAlberto Monje氏は、スペインのバダホスでインプラント、歯周病治療を専門として開業するかたわら、カタルーニャ国際大学(スペイン)やミシガン大学(米国)、ベルン大学(スイス)などでも活動している気鋭の研究者であり、臨床医である。情報処理の能力、分析力はすばらしく、若くして世界のインプラント周囲炎の研究と臨床をリードしている。今後のますますの活躍が期待される存在である。
未知の疾患から臨床への道へ
848頁の大著が示す臨床のヒント
2000年代に入り、インプラント治療の応用が急速に拡大するにともなって、インプラント周囲炎の問題がクローズアップされるようになった。「未知」であり、「解決不可能」な疾患としてにわかに注目され始め、私たちに大きな不安と戸惑いを与えた。当初、インプラント周囲炎の病態や治療方法に関する情報は乏しく、私たちはSchwarzやRenvertの書籍を頼りに手探り状態で対応を行ってきた。現在でもインプラント周囲炎の発症のメカニズムや細菌叢の詳細など、いまだに不明な部分は多いものの、臨床の現場では少しずつ良好な経過を示す臨床例も増えてきた。このようなタイミングで本書が出版されたことは朗報であった。
本書は、848ページ、全22章におよぶ膨大なページ数の書籍となっている。臨床写真は鮮やかで、美しく、そして大きく拡大されて掲載されているため、思ったよりもスムーズに読み進めることができる。ここでは、印象的な部分をいくつか紹介したい。
早期診断が治療成績を左右する
リスク因子の特定と骨欠損の分類
1章から3章までは、インプラント周囲炎の概論に始まり、主として診断に関連する内容が書かれている。なかでも、3章でインプラント周囲炎に対する早期診断の重要性が強調されていることに着目したい。早期診断のための必須事項として、リスク因子の早期かつ正確な診断が重要であることが述べられている。また、インプラント周囲炎に対する診断法としてプロービングの重要性と手法、そしてその弱点、さらに進化してきたバイオマーカーによる診断についての記述があることも興味深い。また、本書の編者(著者)であるMonjeとWangらは、インプラント周囲炎の骨欠損を分類したうえで、それぞれの骨欠損形態の出現率を評価し、治療指針を示したことでも注目されている。
組織寸法と交絡因子から読み解く
インプラント周囲炎
4章から9章までは、インプラント周囲炎に関連するフェノタイプ、インプラント周囲軟組織、インプラント周囲硬組織の寸法の重要性が詳しく述べられている。これらの内容は、近年、特に注目されており、治療結果を左右する重要な項目でもある。
近年、特に軟組織の厚み(高さ)が荷重後の辺縁骨の吸収と関連していることから、不足部位においては軟組織の造成を考慮すべきとの記載は新しい見解である。 硬組織の問題ではインプラント頬側骨の厚みの重要性が強調される。組織学的見地からは1.5mm以上の十分な頬側骨の厚みの存在により生理的骨レベル、病理学的骨レベル共に安定していることが確認され、臨床医は長期的な成功のために欠損部にインプラントを埋入した場合に寸法の変化を予見しておく必要性が述べられている。そしてこの厚みの概念を理解したうえで、必要に応じてGBRなどの骨造成が推奨されている。
インプラント周囲組織の健康を維持するための角化粘膜の幅や厚みの問題は、長い間議論の的となっていた。しかしながら近年インプラント周囲軟組織、特に角化粘膜の幅や厚みは審美性の獲得や清掃性のみならず、インプラント周囲硬組織の維持安定においても重要であることが示唆されている。
7章では、インプラント周囲炎の局所的な交絡因子(素因、誘発因子、促進因子など)が詳細に解説されており、交絡因子の一覧は非常に役に立つ。これらのリスク因子を識別し、理解し、評価することは、個々のインプラント周囲炎症例に対する治療に役立つのみならず予防やメインテナンスの観点からも重要である。
革新的プロトコルEP-DDSと臨床応用
14章から治療の実際が始まる。18章パート2では、革新的なプロトコルであるEP-DDSが紹介されている。EP-DDSとは、原因の特定(Etiology identification)、一次創傷閉鎖(Primary wound closure)、デブライドメント(Debridement)、除染(Detoxification)、および創傷部の安定(Stability of wound)を意味する、たいへん有望な代替骨再建療法であると考えられる。
さらに19章と21章では、従来難しいとされてきたインプラント周囲軟組織のトラブルへの対応が世界的に著明な著者らにより解説されている。
このように世界トップレベルの歯科医師らにより執筆された膨大な情報が収載された本書の翻訳に、多くの時間と情熱を傾けられた監訳の森本太一朗先生、小川雄大先生、松成淳一先生をはじめ、すべての訳者の先生方に敬意を表したい。