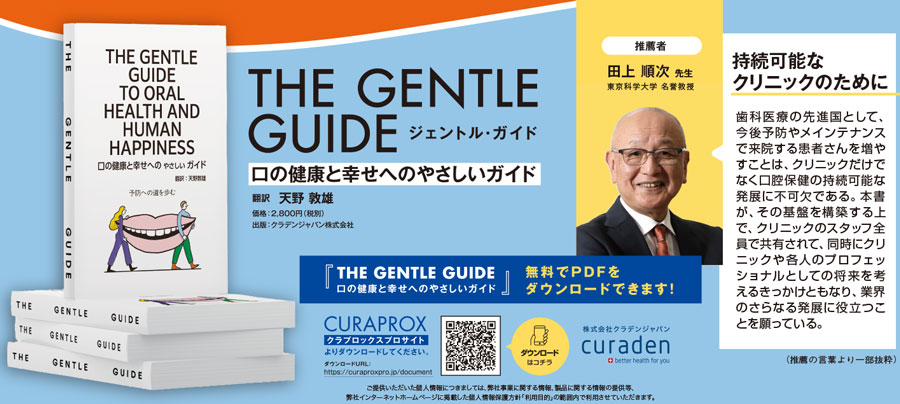2025年9月号掲載
New Frontier—歯科臨床が、変わる・動く・広がる— 『THE GENTLE GUIDE』日本版刊行記念企画 歯科メインテナンスにおける変遷と世界の潮流
※本記事は、「新聞クイント 2025年9月号」より抜粋して掲載。
2025年6月、厚労省から令和6年歯科疾患実態調査の結果が公表され、8020達成者率は61.5%となり、6割を超えた。この結果は、歯科医療の発展とともに歯科医療従事者による予防の推進によって、国民の歯や口の予防に対する意識が高まってきた証左といえるのではないだろうか。 このたび、クラデンAG社(スイス)が『THE GENTLE GUIDE』を刊行し、その日本語版『THE GENTLE GUIDE 口の健康と幸せへのやさしいガイド』(株式会社クラデンジャパン刊、9月15日発売)が完成した。 本欄では、翻訳を担当された天野敦雄氏(大阪大学名誉教授)と推薦文を寄稿された田上順次氏(東京科学大学名誉教授)の歯科界を代表する両氏に、日本における歯科メインテナンスにおける変遷と予防歯科をより広めるための本書の活用法などについてうかがった。
(編集部) 聞き手:池亀 友(株式会社クラデンジャパン代表取締役社長)
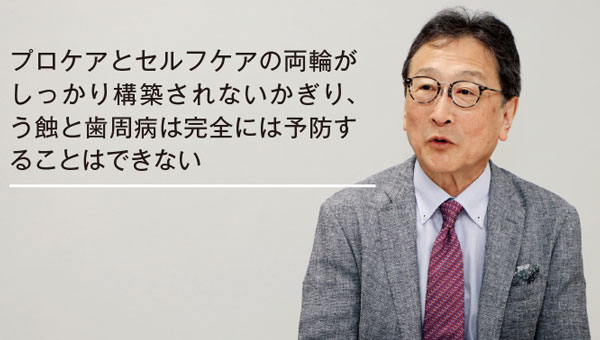
歯科メインテナンスの変遷治療中心型から予防管理型へ
池亀:両先生におかれましては、長年にわたり歯科領域の研究および臨床の第一線でご活躍されてこられました。そのなかで、日本の歯科界においてこれまでの予防を含めたメインテナンスの変化と最近の国民の意識や関心の変化について、どのように感じられていますでしょうか。
田上:私は専門が保存修復分野ですので、う蝕を削って治療する領域です。もちろんその治療法も近年では変化してきています。とはいえ、その治療を長持ちさせるために必要なのは、やはりその後の定期的なプロによるメインテナンスとセルフケアを含めた口腔ケアになります。
世界的な潮流としては、できるだけう蝕にならないような状況を保つという意味での予防が重要視されてきました。しかも、初期う蝕の際にすぐに削らずに進行を抑制させる方法や、再石灰化させて治癒させるというような流れにシフトしてきました。
日本においては、今でこそMI(ミニマルインターベンション)の考え方は当たり前になってきています。私が教授となった1995年には一部のクリニックでは予防を歯科医院経営の1つとして取り組まれていましたが収益につながりにくく、なかなか一般的には広がりませんでした。なぜなら日本における予防処置は歯科保険の対象外(保険外)だったからです。
池亀:近年、予防歯科が普及してきた理由の1つとして保険制度の影響があるということですね。
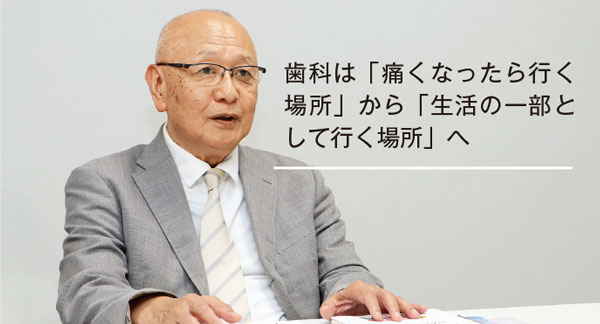
田上:そうですね。ターニングポイントの1つとしては、2008年に保険収載されたSPT(歯周病安定期治療)によって、その継続的なメインテナンスが保険算定できるようになったことは大きいでしょう。さらには、2020年の診療報酬改定によって予防歯科が保険適用になりました。このように日本では保険制度上の体制が整備されはじめたことで、それを臨床に取り入れて対応する必要が出てきましたので、クリニック側にも予防の考え方が普及していきました。
ただ、予防の考え方が多くの患者さんに広がっているかというと、まだまだそうとは言いきれないところはありますが、患者さんの意識が変わってきたのは明らかですね。
近年、患者さんはう蝕の治療はもとより、補綴治療でも歯を削るという治療行為をできるだけ避ける傾向にあります。特に私が勤務するクリニックでは、MI治療をアピールしていて、そのような情報を待合室で映像として流すことで、その治療の希望者が増えています。また、教育現場においても学生にはすぐに治療するのではなく、まずは口腔内の環境を整えることの大切さを伝える教員が増えていますね。
天野:昭和時代の歯科医療は「削って・詰めて」の繰り返しであり、歯科医院は「痛くなったら行くところ」だったわけです。う蝕と歯周病は予防できる疾患ということがわかっていましたが、残念ながら予防歯科は田上先生がおっしゃるとおり、歯科保険の対象外だったわけです。しかし、その後の先人たちのご尽力により、最近では重症化予防という扱いで保険算定できるようになったことで、歯科医院経営を支える1つとして徐々に歯科医師の意識が変化してきました。
池亀:先ほど田上先生が「予防の考え方が多くの患者さんに広がっているかというと、まだまだそうとは言いきれない」とおっしゃられました。天野先生はいかがでしょうか。
天野:私も同じ意見です。その理由は、つまりプロケアを行えばそれで予防ができると思っている歯科医療従事者が依然として多いからです。口腔内の悪玉菌は追い出せず細菌の数を減らすことしかできません。また、いくら歯磨きや洗口剤で悪玉菌の数を減らしても、う蝕菌の場合は約7 時間、歯周病菌の場合は約24時間で元に戻ると言われています。ですから毎日3回歯磨きが必要なのです。2、3か月に1回のメインテナンスで来院してもわずか年4~6回ですよ。どんなに歯科衛生士が頑張っても患者さんのセルフケアが十分でなければ、口腔内の環境を保てるはずがありません。う蝕と歯周病は予防できる疾患ですが、プロケアとセルフケアの両輪がしっかり構築されないかぎり、う蝕と歯周病は完全には予防することはできません。もちろん良い方向に変わりつつあるとは思いますけど、道半ばでゴールはまだ先でしょうね。
池亀:これまでの歯科医療は、天野先生のご指摘のとおり「削って・詰めて」という治療中心型の考え方でしたが、時代の流れとともに「治療から予防へ」という「予防管理型」の考え方に変化してきたことで、プロケアとセルフケアのさらなる充実が求められますね。
田上:予防への意識の高い先生方にしてみれば、自分たちがこれまで取り組んできたことにようやく社会が追いついてきた感じでしょう。保険制度が充実してきたことで歯科医療提供側、行政側、そして患者さんそれぞれのメリットがあるわけです。特に最近は口腔と全身の健康の関係性が注目され、医療費の抑制にも寄与できるというデータも出てきています。
私は以前から歯科は「痛くなったら行く場所」から「生活の一部として行く場所」とお伝えしています。たとえば、定期的に散髪屋に行くように、クリニックに行って口の中をキレイにするような日常生活の一部として、メインテナンスに取り組んでいくことが今後ますます求められます。
天野:いまや歯科医院の経営の一端を支えているのは、歯科衛生士を中心とするメインテナンスや保健指導ですし、予防歯科は立派なその柱になりつつあります。私が大学を卒業した1984年は、補綴治療と外科治療が全盛でしたから、予防歯科学講座に残ると決めた時、クラスメイトに「お前は人生を棒に振る気か」って冗談を言われるほど、予防という意識はありませんでしたので隔世の感がありますね。
令和の指導は「ティーチング」から「コーチング」へ
池亀:歯科メインテナンスを成功に導くためには、歯科医院側の患者さんへのアプローチとして、口腔に関する関心やセルフケアの意識を高めることが重要になってくると思います。そのアプローチする際のポイントなどについてアドバイスをお願いいたします。
田上:歯科衛生士がTBI(歯磨き指導)を行う場合、それぞれの患者さん全員に画一的な口腔ケア指導はしませんよね。患者さんの中には、フロスや歯間ブラシを使ってていねいに歯磨きする方がいれば、それほど細かく磨かない方や磨けない方もいます。そのため、患者さん一人ひとりに応じたアプローチが必要です。そこで、患者さんに関心をもっていただけるような新しい情報をわれわれが毎回少しずつでいいので提供するわけです。たとえば患者さんの健康状態や生活習慣、趣味・嗜好などをカルテとともにメモしておいて、他の人にも紹介したくなる心に残るようなアドバイスをするとより良い関係が構築できると思います。
天野:最近は保健指導やTBIの方法も昭和の頃と比べると大きく変化してきました。昭和の時代の「ティーチング」から令和の時代は「コーチング」に変わったのです。それぞれの患者さんに合わせた口腔衛生指導を行う場合にも、たとえばプラークの付着や歯肉から出血した場合でも、簡単に答えを教えるのではなくその原因について患者さんに考えていただくように声掛けします。また患者さんは、歯が立体的であることを理解していませんので磨きにくい場所がある理由などとともに考えるようにうながし、歯間ブラシやフロスの活用法など、患者さんに気づきを与え、みずから答えを導き出すようにサポートすると良いでしょう。
そのためには、とにかく患者さんの話を聞く「傾聴/アクティブリスニング」が大切になります。とはいえ、自由診療とは異なり、保険診療のなかで患者さんとのコミュニケーションに多く時間を割ける歯科医院はありませんので、コーチングによるアプローチが求められます。細かくゴールを設定して時間をかけて1つずつ指導し、患者さんがその都度目標を達成できたらとにかく「褒める」。そうすることで患者さんのセルフケアが上達し、モチベーションも上がることで後戻りしなくなります。
たとえば、私は患者さんに「この調子で頑張ってくださいね」とは言わず、「今日はすごく歯がきれいでまぶしいぐらい!今よりもっときれいになったら私の目が潰れてしまいますわ」というように言って励ましています(笑)。
田上:医科は病気が治ったらかかわりがなくなることが多いですが、歯科の良いところは患者さんの健康だけでなく生活を支えるというところですよね。患者さんと一生付き合うとか、その患者さんだけでなく子どもや親、親戚を連れてくるなど、世代をまたいで輪が広がるというのがかかりつけ歯科医の特徴であり、それを実現しているのが成功しているクリニックの姿だと思います。
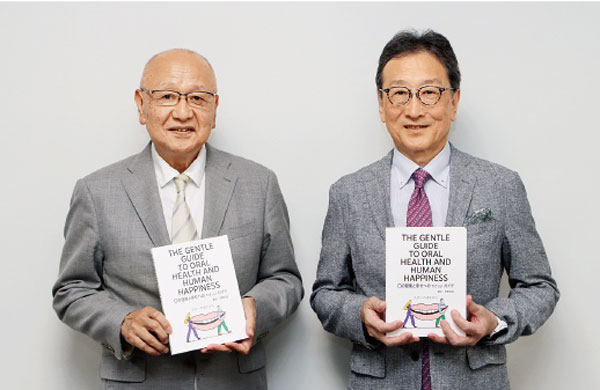
予防歯科の未来がわかる1冊持続可能なクリニックのために
池亀:このたび、クラデン社が『THE GENTLE GUIDE』を出版し、世界の歯科が向かう未来像を示しました。日本語版のタイトルは「口の健康と幸せへのやさしいガイド」としました。
最後に、田上先生には本書の紹介文をご執筆された立場から、天野先生には翻訳者の立場から、本書をつうじて日本の歯科医療従事者ならびに国民へ予防歯科に関する気づきが提供できるのかについてご説明いただけますでしょうか。
田上:本書は、口腔と全身とのかかわりをはじめ、メインテナンスのあり方や教育、コーチングなど、最新情報はもとより将来の歯科医療のあるべき姿が示されています。予防歯科に携わる歯科医師と歯科衛生士としては、一回読んで情報を整理しておくと良いでしょう。
その中ですべて実践するのではなくて患者さんの状態、あるいはクリニックの診療スタイルを考えながら取り組んでいくなかで、先ほど述べたように患者さんに関心をもっていただけるような最新トピックスとして情報提供していただければと思います。そして、本書をつうじて予防歯科にかかわるすべての歯科医療従事者の知識のアップデートができることを願っています。
天野:本書は第1章「予防が一番」、第2章「口腔の健康は全身の健康に影響する」、第3章「口腔保健コーチング」、第4章「患者に自分の口腔内の美しい菌叢を気づかせる」、第5章「私達が実践し実現すること」、第6章「セルフケアの連鎖」、最後に「口の健康と人間の幸福の4つの柱」の7部で構成されています。そして、予防歯科に関する最新の論文が掲載されていますのでご活用いただけると思います。また、クラデン社が推奨するiTOP(個別訓練型口腔予防法)について、この方法を普及させるために必要な内容が詳しく解説されています。
最近では、インターネットで歯科に関する情報を簡単に入手できるので、患者さんの中にも詳しい方が多いですよね。私たちもその詳しい患者さんの疑問や質問に的確に答えられるような正しい知識をもっておく必要がありますので、ぜひ本書を読んで知識のアップデートをおすすめします。
池亀:著者には多くの歯科医療従事者とコーチングの専門家だけでなく、クラデンiTOPセミナーに参加した歯科プロフェッショナルも参画しています。本書は自院で予防歯科を導入・検討したい先生方や歯科衛生士に読んでいただきたい内容となっています。
田上:歯科医院経営的には、予防とメインテナンスの患者さんをいかに増やすかが課題になります。その中心となるのが、歯科衛生士の皆さんです。現在、歯科衛生士の人材不足が課題として挙げられていますが、歯科衛生士が活躍できる医院づくりが今後求められますので、本書の推薦文にも示したとおり「持続可能なクリニック」のためにも役立てていただければ幸いです。
――本日はありがとうございました。