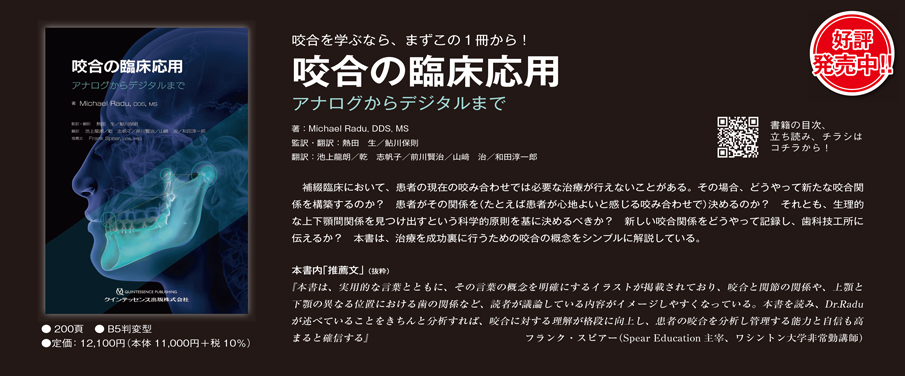2025年12月号掲載
わかりやすい図と解説でシンプルに理解できる
【PR】 咬合の“重要性”を説くのではなく、その“実践”にこだわった話題の書
※本記事は、「新聞クイント 2025年12月号」より抜粋して掲載。
歯科医学のなかでも、“咬合”は難解なものというイメージがつきまとい、これをテーマとする書物もまた同様です。そのようななか、2024年、米国で『Practical Applications in Dental Occlusion:Analog to Digital』というきわめてシンプルでかつ実用的な咬合の書が出版され、このたびその日本語版『咬合の臨床応用 アナログからデジタルまで』が出版されました。本欄では、その著者であるMichael Radu氏に、本書の出版経緯や特長をうかがいました。(編集部)
咬合軽視の世界的な傾向
私はこれまで30年以上、さまざまな国で咬合についての講義をしてきましたが、その間、多くの歯科医師から「咬合はよくわからないもの(=Occlusion is Confusion)」と言われてきました。
また、私が開業している米国では、「咬合の知識なんてそんなに必要ないし、なくても十分に治療が行えている」と考える歯科医師が多く、その重要性は軽視されています。ただし、このことは米国に限ったことではなく、これまで欧米3か国で診療を行い、多くの国の歯科医師を見てきた私の経験からすると、世界的に同様の傾向にあると感じています。
理論が先立つ咬合学
一方で、私を含め、咬合を非常に重要なものだと考える歯科医師はどこの国にも一部いて、そういった歯科医師らによって、これまで咬合をテーマとする本がたくさん出版されています。
それにもかかわらず、なぜ、咬合が軽視されるのでしょうか。私はある時、咬合は理論や専門用語がどうしても先立ってしまい、臨床において具体的に何を行うべきか、すなわち実践的なアプローチ法があまり教えられていないからではないかと考えました。
咬合の“重要性”を説くのではなく、その“実践”にフォーカス
そこで私は、咬合の実践に特化した本を書きたいと考え、その企画書をクインテッセンス出版(米国)に送りました。すると、「弊社が咬合の本に求めていたのは、まさにこういう(実践的な)内容です」と、返事があり、本書『咬合の臨床応用』の執筆をスタートさせました。
ちなみに、私の友人は当初、「咬合の本なんて書くべきじゃない、すでに山ほどあるじゃないか」と執筆に大反対でした。たしかに、私の書庫にも咬合関連の本はすでに42冊もありましたから、そう思うのも無理はありません。
しかし、これに対して私は、「わかっているよ。ただ、私が書きたい内容は(これまでのような)咬合の“重要性”を説くものではなく、その“実践”なんだよ」と答えました。そのようなこともあり、本書はよりいっそうシンプルで、かつ実践的な内容にしなければなりませんでしたが、これには非常に苦労しました(笑)。しかし幸いなことに、Leahさんという有能な編集者が私の原文を見事に推敲・編集してくれて、すばらしい本に仕上げてくれました。
専門用語は極力、排除
本書では実際の臨床で使用しない咬合の専門用語――たとえば、「スピーの湾曲」、「ウィルソンカーブ」、「イミディエイトサイドシフト」、「ベネット角」等々の咬合に関する専門用語は一切出てきません。それらの用語の使用は実際の臨床では必要ないですし、咬合を学ぶことを歯科医師から遠ざけるものだとも思います。また、「中心咬合位」という言葉も、その用語集における定義に私が同意しかねるため、使用していません。さらに、私には「下顎が中心位にあるとき~」という表現にも異議があります。なぜなら、中心位という概念は、下顎位を完全には説明するものではなく、本当に重要なのは下顎位そのものであり、下顎頭がどこにあるかだけではないからです。
主題は2つの咬合
実際の臨床で咬合においてまず考えるべきは、“その患者さんの既存の咬合を変えないで治療が行えるか否か”だと私は考えています。そのため、本書においてはこのことを起点にして既存の咬合を“変えなくてよい場合”と“変えなければならない場合”の2つに分けて、それぞれの治療の進め方をアナログとデジタルの双方によるアプローチで解説しています。
私の恩師はPeter E. Dawson先生で、私は彼から咬合のすべてを学びました。Dawson先生は残念なことに本書の完成に間に合うことなく他界されましたが、生前、私が咬合の本を書いていることを知り、「Michael、臨床の基準(bar)を下げてはいけないよ」と私に言いました。Dawson先生は「すべての咬頭嵌合位は中心位と一致すべき」という考えでしたので、既存の咬合を“変えなくてよい場合”があるという本書の一方の考え方を妥協的な治療ととらえて容認しなかったのです。
私はこれに「Peter、私は基準を下げるつもりはありません。ただ、その基準から一歩離れて、その基準がどういうものかを見極め、“変えなくてよい場合”と“変えなければならない場合”を判断すべきだと思うのです」と答えました。本書では当然、中心位を基準位にした臨床についても十分に論じていますが、その一方でつねに中心位である必要はないし、中心位にできない場合もあるわけです。このことは咬合における永遠の議題で、多くの歯科医師はこの話題を避けたがりますが、本書の主題はまさにこの点にあり、私はその真実を書いています。
若手歯科医師にぜひ読んでほしい
本書は万人向けの内容ですが、咬合に関する固定観念をもたないオープンマインドな若手歯科医師によりフィットするかもしれません。ぜひ、ご一読いただければと思います。(談)